|
|
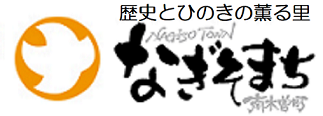 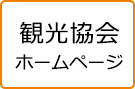 |
 |  |  |  |  |
| 昭和55年に国の伝統的工芸品に指定されました。工場見学もできます。 ろくろ細工は厚い板や丸太をろくろで回転させながらカンナで挽いて形を削り出す伝統技術です。 南木曽地域では江戸時代から、木曽谷に育つケヤキ、トチ、センノキ、カツラなど木目の美しい広葉樹をろくろで挽き特産として盛んに造られてきました。代々引き継がれてきた職人技は木目の美しさ、手触りのやさしさが特徴です。 伝統的工芸品産地・南木曽ろくろ工芸協同組合 〒399-5302長野県木曽郡南木曽町吾妻4689 電話0264-58-2434 |
| 事業所名 | 電話番号 | 備 考 |
|---|---|---|
| 工房ヤマト小椋商店 | 0264-58-2144 | 見学もできます |
| カネキン小椋製盆所 | 0264-58-2021 | 見学もできます |
| ヤマイチ小椋ロクロ工芸所 | 0264-58-2041 | 体験及び見学もできます |
| 神原漆器工芸所 | 0264-58-2020 | 漆塗りのみ |
| 田上民芸 | 0264-58-2205 | 各種お椀、こね鉢他ろくろ製品。漆は素地に直接塗り、一日1回最低6回、製品により7~8回と塗りこんで仕上げます。地球環境に優しい安全食器を皆様に御勧めいたします。 |
| 野原工芸 | 0264-58-2330 | 漆塗りの他、木のボールペンもあります。 |
| ヤマダイ大蔵 | 0264-58-2052 | 見学もできます |
    |
| 木曽の名産である木材を使用した各種製品の製造、販売をしています。 |
| 事業所名 | 電話番号 | 主な製品 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 木曽檜木創 | 0264-58-2039 | 回転盛皿、濡れ縁、座机、桶製品、ラック | 店内には数多くの木曽ひのき製品が並びひのきの香りがいっぱいです。 |
| 進興工芸 | 0264-57-2023 | 寿司盛り皿・菓子器など、ひのきの赤節製品 | 木曽ひのきの赤節特有の色味を生かして、独自の技術とノウハウで開発した商品です。 |
| 志水木材産業 | 0264-58-2011 | 桶製品 | ホームページをご覧下さい。 |
| なぎそ工芸 | 無垢材使用の手づくりオーダー家具 | オーダーならではの愛着と使い勝手の良差・・・お客様の満足がすべてです。 | |
| 木曽五木工芸社 | 0264-58-2213 | ひのき名刺 ひのきはがき | 木曽ひのきをスライスした、はがき・名刺など。当社のみのオリジナル商品 |
| どんぐり工房 | 0264-58-2278 | ろくろ製品 | 大道芸も披露する田舎名人。自作のろくろ製品を使ったうどん作りも名人肌 |
| 原製作所 | 0264-58-2040 | 水車 | 観賞用のミニ水車(径30cm)から動力水車、揚水水車(径5m)まで受注生産いたします。(観賞用は常時在庫あります) |
| 可児工芸 | 0573-75-4755 | ひのきはし等の木製品 | 麺類を食べるときでも滑らないよう加工してあり、独特の手ざわりと併せて使い良さ抜群の箸です。 |
| 楯木工製作所 | 0264-57-2300 | 木曽桧・さわら各種木工製品製造 | 木工製品のことなら何でもご相談ください。 木曽桧・さわら木取材有り。特殊木工加工 |
 |
| 昭和57年に長野県伝統的工芸品に指定されました。制作体験や実演も見学できます。 蘭桧笠作りは、1662年に岐阜県飛騨地方から伝えられた技法で、当時、耕地の少ない蘭では、たちまち主要産業になりました。年に10数万枚、明治時代の最盛期には100万枚近くの生産量を誇りました。伝統技術による手作りの良さが見直されて、現在でも農作業の他に登山や舟下り、魚釣りなどを中心に“実用笠”または“装飾品”として、地元民だけでなく観光客にも人気を集めています。歴史が長く、何年、何代も受け継がれてきており、現在(平成28年)では350年余の伝統工芸品となっています。 蘭桧笠生産協同組合 〒399-5302長野県木曽郡南木曽町吾妻3900 電話0264-58-2664 |
| 事業所名 | 電話番号 | 備 考 |
|---|---|---|
| ひのき笠の家 | 0264-58-2727 | 「心細いよ木曽路の旅は 笠に木の葉が舞いかかる」と木曽節に唄われている桧笠は美しい網目、桧の香りとともに木曽の自然と素朴な生活風土が生かされています。 |
| 蘭桧笠生産協同組合 | 0264-58-2664 |
  |
| 「ねこ」は、信州・南木曽町に昔から伝わる防寒着です。 南木曽町の伝統的工芸品・ろくろ細工、桧笠などの製作の際、邪魔にならないように袖なしにし、冷える背中だけを暖めるように工夫されてきました。 また、「ねこ」は、昔から各家庭に伝わる型・手法で手作りされています。そのため、作り手さんによって形や作り方が少しずつ異なっています。手作りならではの着心地で、つい着ていることも忘れてしまいます。色々な柄や素材がありますので、ぜひ、ご自分にあった「ねこ」を見つけてみてください。 「ねこ」の名前の由来は、「ねんねこ半纏から」、「作業している姿が猫背だから」、「猫のように温かい」など諸説あります。 |
| 事業所名 | 電話番号 | 備 考 |
|---|---|---|
| 槌屋 | 0264-57-3175 | 妻籠宿場内 |
| 高麗屋 | 0264-57-3113 | 妻籠宿場内 |
| 吉村 南木曽ねこ製作所 | 0264-58-2450 | 電話・HP通販可能 |
| 野原工芸 | 0264-58-2330 | 国伝統工芸品ろくろ細工販売店 電話・HP通販可 |
| 萬屋 | 0264-24-0787 | キッチン&カフェ |
  |
| 田立は古くから和紙の里として知られ、江戸中期に既にこの地で紙漉きが行われていた記録が残っています。「田立和紙の家」は、この伝統ある田立和紙の技術を保存し、多くの人に知ってもらおうと、町が山村振興事業で昭和60年(1985年)に復元したものです。ここでは、楮(こうぞ)100%の原料での丈夫で素朴な本物の和紙の手漉きをご体験いただけます。(1週間前に予約して下さい。 田立和紙の家(田立和紙保存振興会) 〒399-5303長野県木曽郡南木曽町田立233 電話0573-75-4910 ※冬場のみ 代表者宅:tel 0573-75-5066 |
| ||
 | ||
〒399-5301 | ||
TEL:0264-57-2001 FAX:0264-57-2270 | ||
●開庁時間● 8時30分~午後5時15分 | ||
Copyright © Nagiso Town, All Rights Reserved. |